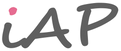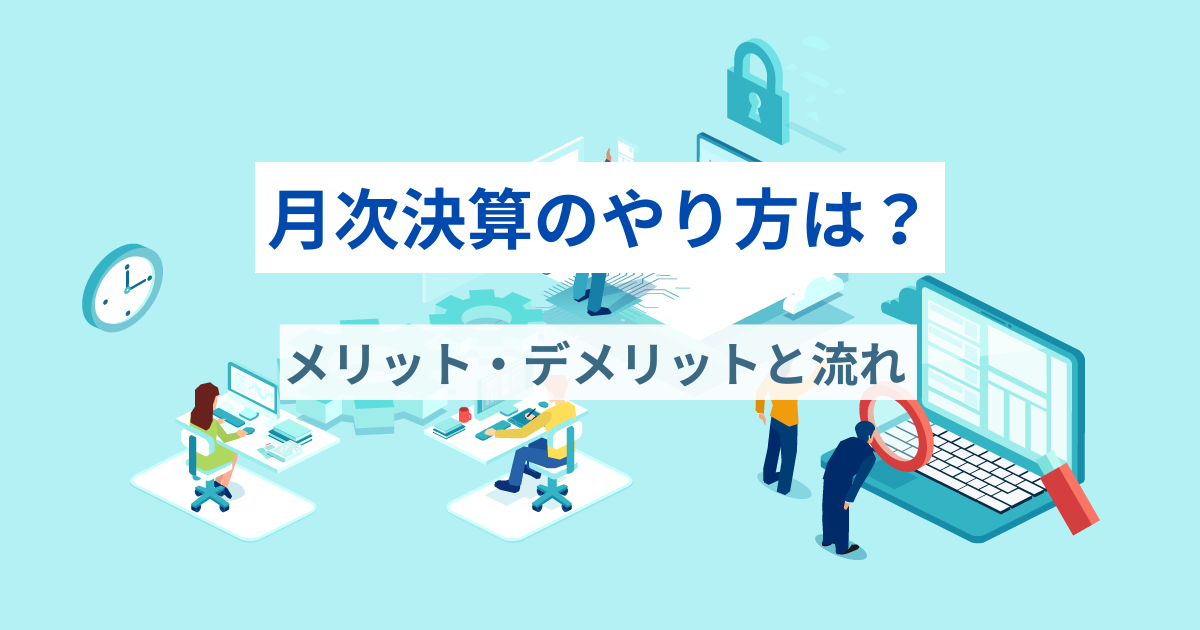「年次決算だけでは経営状況の変化に気づくのが遅れてしまう」「企業として毎月の数字を把握したい」と考えているのであれば、月次決算を導入する方法があります。
しかし、経理担当の負担が増えそうでなかなか導入に踏み切れないケースもあるでしょう。
そこで、本記事では月次決算の定義や目的、担当者の負担を抑えるためのやり方などについて解説します。
この記事を読むことで月次決算運用のポイントがわかるようになるので、ぜひ参考にしてください。

月次決算とは?

月次決算とは、月ごとの財政状態を把握し、経営管理に役立てるために、企業が毎月行う決算処理のことです。
目的
月次決算を行う大きな目的は、現状を定期的に把握し、迅速な経営判断につなげることにあります。
会社の損益や財産がどのような状況になっているのか毎月可視化することで正確な財務状況を把握するためのものです。
月次決算を実施することで、1年間の売上や利益目標がどの程度達成できているのか、また順調に事業が進んでいるかなどの判断につなげられます。
年次決算との違い
企業によっては、年1回のみの決算を実施している企業もあります。
年次決算は、1年間の会計期間を締め、税務申告を行う決算のことです。
しかし、年1回のみの決算では損益が変動していても、早期に対策を取れず経営判断が遅れる恐れがあります。
一方、月次決算の場合も年次決算と同様に会計処理を行う形となりますが、毎月決算をすることで企業の状況を把握しやすくなり、スピーディーな経営判断につなげられます。
それから、年次決算はすべての会社に義務付けられているものであり、必ず行わなければなりません。
事業年度終了後2か月以内に作成を終える必要があり、その正確性も求められます。
月次決算は法律で義務付けられておらず、書式も自由です。
自社でテンプレートを作成するなどして取り組んでいく形となります。
月次決算は経営判断に必要な数字を迅速に求めるのに対し、年次決算は法的報告のための会計です。
月次決算のメリット
月次決算を行うことで、さまざまなメリットがあります。
特に経営状態をタイムリーに把握できるようになるほか、年次決算・税務申告がスムーズにできるようになる点は重要です。
他にも金融機関から融資を受けやすくなる、経営判断のスピードと精度が向上するなど、多くのメリットが得られます。
それぞれ解説します。
経営状況をタイムリーに把握できる
企業が経営判断を迫られた場合は、データに基づいて判断することが重要です。
月次決算を行うことで経営状況をタイムリーに把握できるようになり、判断に必要な数字を根拠として提示しやすくなります。
勘に頼るのではなく、数字に基づいた行動が取れるようになるのは大きなメリットです。
年次決算・税務申告の準備がスムーズになる
特に従業員が不足している企業の場合、月次決算は担当者の負担が大きくなるデメリットを重視してしまうことがあります。
しかし、月次決算を実施しておくことで年次決算・税務申告の準備をスムーズに進められるのがメリットです。
月次決算を行っている場合は、日常的に会計データが整理されている状況になります。
そのため、年末に帳簿や領収書をまとめて処理する必要がなくなり、担当者の決算業務に関する負担を抑えられます。
これは、年末に決算業務が集中してしまうために発生しやすいミスを抑えることにもつながるポイントです。
月次決算は1か月ごとに計算を行うことになるので、決算において何か確認しなければならないことがあったとしても、さかのぼって情報を調べなければならないのは1か月前までとなります。
一方、年次決算のみの場合は、数か月前の情報をさかのぼって調べなければならないこともあり、非常に大変な作業といえるでしょう。
決算期の業務量や担当者の負担を大幅に軽減するためにも、月次決算が役立ちます。
金融機関から融資を受けやすくなる
月次決算を実施しておくことで、金融機関から融資を受けやすくなるメリットがあります。
金融機関は融資を行う際、企業の現状を確認する必要がありますが、年次決算しか行っていない場合は最新の状況を把握しづらくなります。
前年度の成績が良かったとしても、直近の業績が大幅に悪くなっている可能性も考えられます。
一方、月次決算の報告書を提出できれば金融機関は最新の企業の状況がわかるので、スムーズに融資を受けやすくなるのがメリットです。
経営判断のスピードと精度が向上する
月次決算を導入すると、経営判断のスピードと精度の両方が向上します。
リアルタイムで業績を管理できるため、利益が下がっている部門があれば原因を特定し、早急な改善につなげられます。
好調な事業には積極的に資金を投入しやすくなります。
これは、企業が利益拡大を目指すうえでも重要な要素です。
月次決算のデメリット
月次決算にもいくつかのデメリットがあります。
特に「経理担当者の負担増」「調整の複雑化」「短期的な業績悪化への過剰反応」という3点には注意が必要です。
1つずつ解説していきます。
経理担当者の業務負担が増える
月次決算を導入すると、担当者の業務負担が増加します。通常の仕訳入力や請求処理に加え、月次決算書の作成も必要となります。
すべてを手作業で対応するのは難しいため、会計ソフトを活用して負担を抑えるようにしましょう。
ただし、ソフト導入には費用がかかる点もデメリットです。
他部門との連携が必要になり調整が複雑化する
月次決算は複数の部署や部門と連携する形で進めていくことになります。
売上や仕入れに関すること、在庫や人件費など、複数部門から情報を集約して行わなければ、正しいデータを得られません。
特に月次決算を導入したばかりの時期は、社内で情報伝達ミスや書類遅延などの混乱が発生しやすくなります。
月次決算の重要性やメリットが社内で共有されていない場合、書類提出の遅れが発生し、全体のスケジュールが乱れる恐れもあります。
情報共有を円滑に進めるための社内体制を整えることも重要です。
短期的な業績悪化に振り回される
月次決算では会社の経営状況をいち早く把握できるようになりますが、その結果を重視しすぎると、短期的な業務悪化に振り回されてしまう恐れがあります。
たとえば、一時的なコスト増にもかかわらず、それを過度に問題視して必要以上にコストを削減し、長期的な戦略がぶれるケースも少なくありません。
月次決算はいち早く経営の方向性を修正する指標として役立ちますが、季節変動や一時的な要因に振り回されないよう注意が必要です。
結果を冷静に分析し、中長期的な視点で対策を考慮することが重要になります。
月次決算のやり方(流れ)

実際に月次決算のやり方を確認しておきましょう。
全体的な流れを把握したうえで取り組んでいくことが重要です。
やり方の基本を解説します。
月次の取引データを確認する
はじめに行うのが、月次の取引データの確認です。
以下のようなデータを収集しましょう。
【収集が必要なデータ】
- 現金・預金:残高が帳簿の内容と一致しているか確認する。
- 棚卸資産:在庫のこと。在庫の数量や単価の整合性を確認する。
- 仮勘定:処理漏れや内容が未確定となっている項目がないか確認する。
- 経過勘定:計上時期を調整するために使用する勘定科目。
- 減価償却資産:当月の償却費分を計上する。
- 引当金:賞与や退職給付といった発生見込みを反映させる。
- 納税充当金:年間費用を見積もり、法人税や消費税などの見込み額を把握する。
仮勘定とは、仮払金、建設仮勘定、仮受金、仮売上高、仮仕入高などのことであり、将来的にどの費用・資産になるか不明な場合に一旦計上しておく科目です。
また、正しい損益を求めるためには現金による収支と、計上すべき収益・費用のタイミングがずれた場合に調整する役割をもった経過勘定の適切な仕訳が必要になります。
未払費用、未収収益、前払費用、前受収益などが主な経過勘定科目です。
正しい経営判断を行うためにも、経過勘定科目を適切に処理しましょう。
各データを丁寧に算出することで、精度の高い月次決算書を作成できます。
月次決算書を作成する
集めた取引データをもとに月次決算書を作成します。
仕分け内容を総勘定元帳に転記していきましょう。
以下のような書類を作成することになります。
【作成する書類】
- 損益計算書
- 貸借対照表
- 資金繰り表
そのほか、受注残高表や在庫一覧表、経費推移表、各試算表なども作成します。なお、法律で定められた形式はありません。
自社の業務内容に応じて必要な書類を選定しましょう。
月次事業報告書をまとめる
まとめた結果は、月次事業報告書を作成して報告します。
同時に現時点での経営成績がどのようになっているかも報告しましょう。
以上が基本のやり方です。
月次決算のポイント
月次決算を実施する際の重要なポイントは、次の5つです。
クラウド会計ソフトを活用する
効率的に月次決算を行っていくためには、各種ツールが役立ちます。
中でもクラウド会計ソフトは優先して導入を検討するとよいでしょう。
データの自動取得や仕訳などの機能により、担当者の行う記帳作業を大幅に軽減できるのが特徴です。
手作業に比べて入力ミスを防げるほか、クラウド型ソフトの導入により情報共有も容易になります。
チェックリストを作成する
月次決算のやり方を紹介しましたが、スピード感をもって対応しなければならないこともあり、漏れを防ぐためにはチェックリストを作成し、手順に沿って進めることをおすすめします。
チェックリストの項目は企業によって異なります。自社の月次決算の流れを整理し、必要な作業を明確にリスト化することが重要です。
毎月行う処理内容を明確化しておくことにより、担当者が変わっても同じ手順で業務を進めやすくなります。
部門間で締め日やスケジュールを共有する
月次決算の締め日や書類提出のスケジュールは、あらかじめ全部門で正しく共有しておくことが大切です。
部門ごとの認識のずれや意識不足により、締め日までに書類が提出されず担当者の負担が増すことがあります。
各部門のシステムを連携させ、共有カレンダーやプロジェクト管理ツールを活用することで、状況をリアルタイムで把握できる体制を整えると効果的です。
経理処理のルールを標準化する
経理処理に関連するルールは、標準化しておきましょう。
担当者によって仕訳方法や処理基準が異なると、月次決算を誰が行ったかによって精度にばらつきが生じてしまう恐れがあります。
細かいルールについてはマニュアル化しておくとわかりやすいでしょう。
アウトソーシングする
月次決算は企業の最新の状況を把握するためにも実践すべきものではありますが、人手不足などの理由から自社での対応が難しいと感じることもあります。
そういった場合は、アウトソーシングについて検討するのも一つの方法です。
特に中小企業の場合は月次決算を開始することで経理担当者に大きな負担がかかりやすくなります。
日々忙しい中で決算業務も行っていくとなると、ミスも発生しやすくなる点に注意が必要です。
経理業務をすべてアウトソーシングすることも可能ですし、計算処理や決算書の作成のみを依頼することもできます。
担当者の負担を軽減することで、コア業務に集中しやすくなります。必要に応じてアウトソーシングの活用も検討してみましょう。
関連記事:給与計算のミス防止策とは?ミスの内容・リスク・原因も解説
経営判断に役立つ月次決算を実施していこう
経営状況を迅速に把握し、的確な意思決定につなげるための月次決算について解説しました。
実施するメリットやデメリットについてもご理解いただけたのではないでしょうか。
担当者の負担が増えることはありますが、年次決算の業務負担の軽減にもつながります。
正しい方法を理解し、継続的に実践することが重要です。
人員が限られており、現状では実施が難しい場合は、アウトソーシングの活用も有効な選択肢です。
iAPでは、専門知識を持つプロフェッショナルチームがワンストップでサービスを提供しています。必要な業務だけを選んで依頼することもできるため、自社の状況に合わせた活用が可能です。