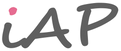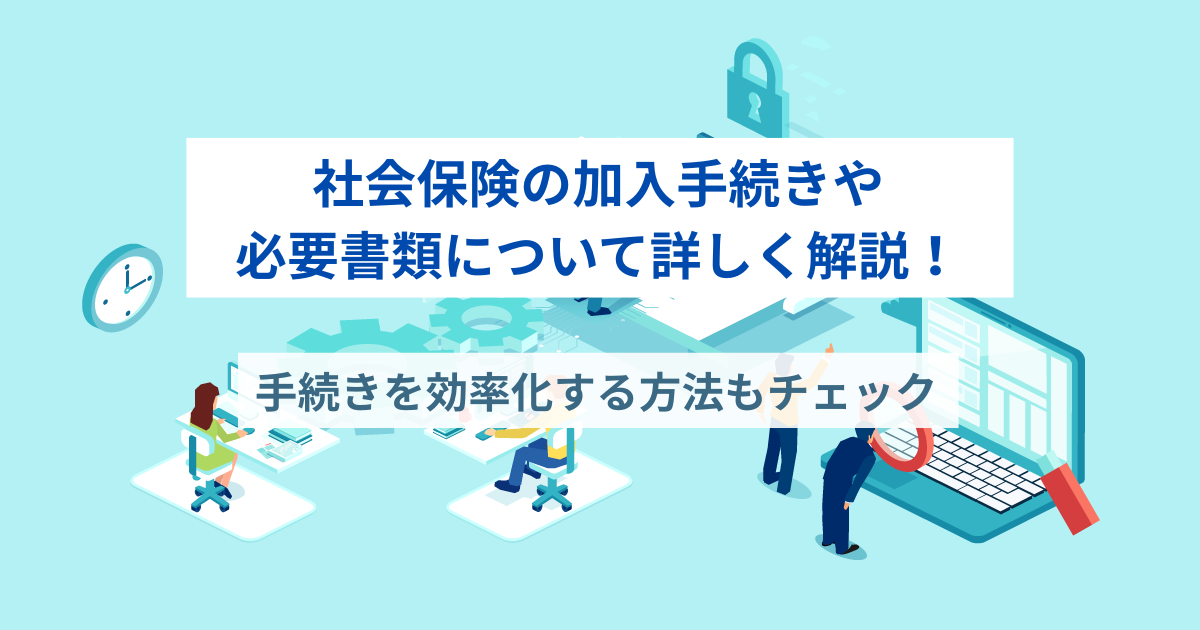社会保険の加入手続きは、企業にとって法令遵守と従業員管理の両面で欠かせない重要な業務です。
従業員の雇用形態や労働時間によって加入要件が異なるため、正確な判定と迅速な届出が求められます。
手続きの遅延や申請漏れは追徴金や指導の対象となり、企業の信頼にも関わるため、この機会に理解を深めておきましょう。
本記事では、事業所側の加入義務や従業員の加入条件、提出書類について解説します。
効率的に進めるためのポイントも整理しているので、ぜひ最後までご覧ください。

社会保険に事業所が加入する義務
社会保険は、従業員の生活を守るために国が定めた制度であり、事業を運営するうえで欠かせない法的義務のひとつです。
すべての法人および一定の条件を満たす個人事業所は、健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入する必要があります。
社会保険の適用対象となる事業所は「適用事業所」と呼ばれ、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」に分類されます。
ここでは、それぞれの違いや加入義務が発生しないケースについて詳しく見ていきましょう。
強制適用事業所
強制適用事業所とは、事業主や従業員の意向に関係なく、自動的に社会保険への加入が義務づけられている事業所のことです。
株式会社や合同会社などの法人は、たとえ従業員が代表者1人のみであっても社会保険の加入対象となります。
また、個人事業所であっても、常時5人以上の従業員を雇用している場合は、原則として強制適用の対象となります。
ただし、サービス業や農林漁業など一部の業種は例外とされています。
つまり、法人であれば規模を問わず、個人事業所であれば一定の従業員数を超えた時点で加入義務が発生する仕組みです。
任意適用事業所
任意適用事業所とは、強制適用の条件を満たさない事業所でも、事業主と従業員の合意によって社会保険へ加入できる制度です。
従業員の過半数が加入に賛同し、事業主が日本年金機構へ申請することで厚生労働大臣の認可を受けられます。
申請が受理されると、健康保険や厚生年金保険の対象事業所として扱われ、強制適用事業所と同様の保険給付を受けられます。
また、希望すれば健康保険または厚生年金保険のいずれか一方だけに加入することも可能です。
安定した雇用関係を維持する小規模事業者にとって、従業員の福利厚生を整えるうえで有効な手段といえます。
加入義務のない事業所
すべての事業所が社会保険に加入しなければいけないわけではありません。
個人事業所で常時使用する従業員が5人未満の場合や、飲食業・美容業・農林漁業など一部の業種では、強制適用の対象外となります。
また、代表取締役のみで報酬が発生していない法人の場合も、加入義務はありません。
とはいえ、条件を満たさない事業所でも、従業員の半数以上の同意を得て申請すれば「任意適用事業所」として社会保険へ加入できます。
安定した事業運営や人材確保のためにも、任意加入を検討する価値は十分にあるでしょう。
社会保険に従業員が加入する条件

社会保険加入の対象となる従業員の範囲を正しく理解しないと、未加入による指導や追徴金などのリスクが生じます。
正社員だけでなく、一定の条件を満たすパート・アルバイト・派遣スタッフなども加入対象となるため、雇用形態ごとの基準を明確にしましょう。
ここでは、企業が把握しておくべき従業員の社会保険加入条件を整理します。
正規雇用(正社員)
正社員は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が原則義務づけられています。
雇用契約の締結時点で自動的に被保険者となり、企業は入社日から5日以内に「被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出する必要があります。
保険料は会社と従業員が折半で負担し、給与計算にも直結するため、経理部門や人事労務部門での正確な管理が求められます。
未届けや遅延が発覚した場合は、遡って加入手続きが必要となり、事務負担やコストが増加するため注意が必要です。
非正規雇用(パート・アルバイト・派遣などの社員)
パートやアルバイトといった短時間労働者であっても、条件を満たせば社会保険の加入義務が発生します。
原則として、週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば対象となります。
加えて、2024年10月の法改正により、従業員数51人以上の事業所では以下4つの条件をすべて満たす場合も加入が必要になりました。
- 週20時間以上の勤務
- 月額賃金8.8万円以上
- 2か月超の雇用見込み
- 学生でないこと
対象拡大により、社会保険の管理対象者が増える企業も多く、勤怠管理・給与計算システムの見直しが求められています。
労務負担を軽減するには、アウトソーシングやクラウドシステムを活用し、加入判定と手続きを自動化する体制を整えることが効果的です。
社会保険の加入手続きの流れ

社会保険の加入は、従業員を雇用した際に必ず発生する法的手続きです。
加入対象者の判定から書類の作成・提出、保険料の納付まで、企業は適切なフローを理解しておく必要があります。
提出期限を過ぎた場合は、是正対応や追徴金のリスクもあるため、ここでスケジュールを明確にしておきましょう。
ここでは、実務担当者が理解しておくべき社会保険加入の基本的な流れを解説します。
各従業員の加入条件を確認する
まずは、採用した従業員が社会保険の加入対象に該当するか確認します。
正社員は原則として全員が対象ですが、パート・アルバイト・契約社員などの短時間勤務者でも、勤務時間や賃金が一定基準を満たす場合は加入義務が発生します。
おさらいすると、2024年以降は、従業員数51人以上の事業所において、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの条件を満たす非正規雇用者も加入対象に含まれるようになりました。
加入対象の誤判定は、遡及手続きや追徴金の発生につながるため、入社時点で条件確認を徹底しましょう。
必要書類を提出する
加入対象者を特定したら、速やかに必要書類を準備し年金事務所または事務センターへ提出します。
代表的な書類は「被保険者資格取得届」や「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」などがあります。
提出期限は原則として事実発生日(入社日など)から5日以内と定められており、遅延した場合は是正指導や追徴対応が求められるケースも。
電子申請システム(e-Gov)を活用することで、業務の効率化や提出ミスの防止につなげられます。
社会保険料を納付する
手続きが完了すると、翌月以降から社会保険料の納付が発生します。
保険料は会社と従業員の折半で負担し、給与から控除した従業員負担分と合わせ、翌月末までに日本年金機構へ納付します。
納付方法は口座振替、金融機関窓口での納付、電子納付(Pay-easy)などがあり、企業の規模や運用体制に応じて選択可能です。
複数拠点をもつ企業では、支払い管理の煩雑化を防ぐため、口座振替の利用やクラウド会計システムとの連携が効率的です。
社会保険料の算定や納付は、給与計算と密接に関連するため、経理・労務部門が連携して正確に処理する必要があります。
社会保険の加入手続きに必要な書類
社会保険の加入時は、事業所と従業員それぞれ準備すべき書類があり、提出期限や添付要件も定められています。
書類の不備や提出の遅延は、手続きの差し戻しや行政指導につながるため、正確な書類管理が不可欠です。
ここでは、企業の経理・人事労務担当者が押さえておくべき主要な書類と目的について見ていきましょう。
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
新たに会社を設立した際や、従業員を雇用し社会保険の適用事業所となる場合に必要な届出です。
法人は原則として会社設立から5日以内に提出する必要があり、個人事業所の場合も常時5人以上の従業員を使用する業種であれば同様に義務が発生します。
添付書類として、法人登記簿謄本や住民票、公租公課の領収書などが求められる場合があるため、事前に準備しておくことが大切です。
被保険者資格取得届
従業員を新たに雇用した際に提出する書類で、従業員の社会保険資格を正式に登録するために必要です。
入社日から5日以内に、年金事務所または事務センターへ提出するのが原則です。
記載内容には氏名、生年月日、報酬月額、マイナンバーなどが含まれます。給与計算や保険料算定の基礎となるため、記入漏れや誤りがないよう注意しましょう。
被扶養者(異動)届
従業員が家族を健康保険の被扶養者として追加・削除する際に必要な届出です。
結婚や出産、離婚、扶養家族の就職など、家族構成の変動があったら提出します。
被扶養者の収入状況や続柄を確認できる書類(所得証明書や住民票など)の添付を求められる場合もあり、提出は原則として、事実発生日から5日以内に行います。
雇用保険被保険者資格取得届
従業員を雇用した際に、雇用保険に加入させるための届出です。
社会保険と異なり、提出先は管轄のハローワークとなります。
提出期限は入社した月の翌月10日までと定められており、雇用保険被保険者証の発行に必要な手続きです。
電子申請にも対応しており、他の社会保険手続きと並行して進めることで、より効率的に処理できます。
賃金台帳・出勤簿・雇用契約書の写し
社会保険の新規適用や資格取得の際、事業所の実態や雇用関係を証明するために添付が求められる場合があります。
これらの書類は、報酬額や労働日数の根拠となり、保険料算定や適用判断の基礎資料として扱われます。
労務管理体制を整備するうえでも、常に最新の内容に更新しておくことが大切です。
マイナンバー(個人番号)を確認できる書類
「被保険者資格取得届」などを作成する際は、従業員本人および扶養家族のマイナンバーを確認できる書類が必要です。
マイナンバーカードのほか、通知カードと身元確認書類(運転免許証など)の組み合わせでも認証が可能です。
これらは事務手続きのために使用するもので、年金事務所への提出は不要ですが、厳重な情報管理が求められます。
年金手帳または基礎年金番号通知書
従業員の年金番号を確認するために必要な書類です。
年金手帳の発行が終了した現在では、基礎年金番号通知書またはマイナンバーによる確認が一般的となっています。
社会保険の資格取得届を作成する際の基礎情報として利用されるため、入社時に必ず確認しておきましょう。
年金番号の誤りは保険料記録の不整合を招くため、提出前の確認を徹底することが重要です。
社会保険の加入手続きを効率化する方法
社会保険の加入手続きは、入社・退職・扶養変更など、従業員の異動や状況の変化に応じて発生する定常業務です。
処理件数が増える時期は担当者の負担も大きくなり、入力ミスや提出遅延のリスクが高まります。
こうした課題を防ぐには、仕組みや体制を見直し、効率的に手続きを進める工夫が必要です。
ここでは、経理・人事労務担当者が実践できる具体的な効率化の手段を紹介します。
マニュアル・チェックリストを作成する
社会保険の手続きを正確に進めるためには、社内で統一されたマニュアルとチェックリストの整備が不可欠です。
業務手順を明確にすることで、担当者が変わってもスムーズに引き継ぎでき、手続き漏れや提出ミスを防げます。
従業員の入社・退職時や扶養追加など、手続きの頻度が高い場面では、必要書類と期限を明記したチェックリストがおすすめです。
メリットとしては属人化を防ぎ、業務の標準化を図れる点が挙げられます。
一方で、法改正や書式変更のたびに内容を更新する必要があり、定期的なメンテナンスが欠かせません。
作成したマニュアルは放置せず、年1回以上見直して、常に最新の手続きを反映させましょう。
クラウドシステムを活用する
クラウド型の人事・労務管理システムを導入することで、社会保険の手続きデータを一元管理でき、作業効率を大幅に向上させられます。
従業員情報の登録や更新、保険料計算、届出書類の作成などを自動化できるため、手入力の手間やミスを減らせます。
複数担当者による同時作業やデータ共有も容易になり、管理体制の透明性も高まるでしょう。
メリットは、業務時間の短縮と入力精度の向上に加え、テレワークなど多様な働き方にも対応できる点です。
ただし、システム導入には初期費用やランニングコストがかかり、操作に慣れるまで一定の教育期間が必要です。
導入時は、自社の業務規模や処理頻度に見合った機能をもつシステムを選定しましょう。
オンラインで手続きする
社会保険の各種届出は、e-Gov(イーガブ)やマイナポータルなどを利用してオンラインで申請できます。
紙書類での提出に比べ、作成・押印・郵送の手間が省け、24時間いつでも申請できる点が大きなメリット。
複数の事業所を運営する企業では、オンライン化により事務負担を大きく軽減できます。
電子申請を導入するには、GビズIDや電子証明書の取得、対応アプリケーションのインストールといった準備が必要です。
導入初期は設定や操作方法の習熟に時間を要するものの、一度体制が整えば、提出期限の管理やデータ修正が容易になり、長期的にはコスト削減にもつながります。
法令遵守と業務効率を両立させるうえで、電子申請は今後の標準的な手段になるでしょう。
アウトソーシングする
社会保険手続きを専門の社労士事務所やアウトソーシング業者に委託する方法もおすすめです。
従業員数が多く手続き件数が増える企業や、担当者が少ない中小企業では、専門家によるサポートで業務の正確性とスピードを高められます。
法改正への対応や書類不備の防止など、自社では対応が難しい部分も、専門家に安心して任せられるでしょう。
アウトソーシングのメリットは、担当者の負担を軽減し、法的リスクを低減できる点にあります。
さらに、経理・人事部門がコア業務に集中できるようになり、生産性の向上にもつながります。
ただし、委託費用が発生するほか、個人情報を外部に共有するリスクも伴います。
契約前にセキュリティ対策や実績、対応範囲を十分に確認し、信頼できる委託先を選びましょう。
関連記事:社会保険手続き代行の最新事例と流れ・メリットを詳しく解説
社会保険の加入手続きに関するよくある質問
最後に、社会保険の加入手続きに関するよくある質問をまとめました。
加入手続きに期限はありますか?
社会保険の加入手続きには明確な期限が定められています。
事業所が新たに社会保険の適用対象となった場合は、要件を満たした日から5日以内に「新規適用届」を提出しなければなりません。
また、従業員を雇用した場合も、雇用日(資格取得日)から5日以内に「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
期限を過ぎると、行政指導や遡及加入の対象となる場合があり、過去分の保険料をまとめて納付する義務が生じます。
特に複数の雇用契約や再雇用などが関係する場合は、日付管理を徹底し、提出期日を社内で共有しておくことが重要です。
保険料の負担はどれくらいですか?
健康保険料と厚生年金保険料は、いずれも会社と従業員が折半で負担します。
健康保険料率は都道府県ごとに異なり、厚生年金保険料率は全国一律で設定されています。
保険料は従業員の標準報酬月額を基に計算され、給与から控除する従業員負担分と、企業が拠出する事業主負担分の合計を翌月末までに納付しなければいけません。
会社としては、従業員の昇給や勤務形態の変更などによる報酬変動が保険料に影響する点に注意が必要です。
標準報酬月額の算定を誤ると、後日修正申告や追加徴収の手間が発生するため、毎月の給与計算時に最新の報酬情報を反映させましょう。
中途採用の場合はどうしたらいいですか?
中途採用者を雇用した場合も、入社日から社会保険の加入手続きが必要です。
前職で加入していた健康保険・厚生年金保険は自動的に引き継がれないため、改めて「被保険者資格取得届」を提出します。
従業員からは、基礎年金番号通知書またはマイナンバー、雇用保険被保険者証などを回収し、正確な情報で申請しましょう。
また、前職の退職日と新しい会社の入社日が同一日の場合は、資格喪失と資格取得が同日に発生するため、年金事務所では「同日得喪」として処理されます。
この場合、再雇用契約書や雇用条件通知書などの添付を求められることもあるため、事前に準備しておくと手続きがスムーズに進みます。
加入手続きを怠るとどうなりますか?
社会保険の加入義務があるにもかかわらず未加入のまま放置している場合、年金事務所による調査や指導の対象となります。
行政からの連絡を無視した場合、過去2年分の保険料を遡って徴収されるだけでなく、悪質と判断された際には、50万円以下の罰金や刑事罰の対象となる可能性もあります。
さらに、未加入期間中に発生した医療費や出産手当金の支給が認められないケースもあり、従業員とのトラブルに発展する恐れもあります。
万が一加入漏れに気づいた場合は、速やかに「被保険者資格取得届」を提出し、遡及手続きしましょう。
国民健康保険・国民年金から切り替えられますか?
従業員が新たに社会保険に加入した場合、以前加入していた国民健康保険・国民年金から自動的に切り替わるわけではありません。
本人が市区町村の窓口で「資格喪失届」を提出し、国民健康保険を脱退する必要があります。
その際、会社で加入した健康保険証や資格取得証明書などの提示が求められます。
切り替えを怠ると国民健康保険料の請求が継続され、二重払いが発生するおそれがあるため、注意が必要です。
企業としても入社時に切り替えの案内を徹底し、従業員が誤って保険料を払い続けることのないようサポートしましょう。
退職時には脱退の手続きが必要ですか?
従業員が退職した際は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出し、社会保険からの脱退手続きをする必要があります。
提出期限は退職日の翌日から5日以内です。資格喪失後は本人が国民健康保険への加入や任意継続手続きなどをしなければいけません。
手続き漏れがあると、会社に対して翌月以降も保険料が請求される場合があるため、退職時に確実に処理しましょう。
再雇用や契約社員への切り替えなどの場合は、「同日得喪」となる可能性もあるため、事前に条件を確認しておくことが重要です。
社会保険手続きを効率化し企業の信頼性と生産性を高めよう
社会保険の加入手続きは、企業にとって単なる事務作業ではなく、法令遵守と従業員の社会的保障を支える重要な業務です。
正確な処理と期限管理を徹底することで、企業の信頼性を高め、従業員が安心して働ける環境づくりにもつながります。
一方で、手続き内容は複雑で更新も頻繁に行われるため、経理・人事労務担当者の負担は小さくありません。
こうした課題を解決する手段として、専門家によるアウトソーシングの活用が注目されています。
iAPでは、社会保険をはじめとする人事・労務業務の代行サービスを提供し、煩雑な事務作業を効率化。
最新の法改正にも迅速に対応し、貴社のバックオフィスを強力にサポートします。
人事・労務の最適化を通じて、企業の成長と従業員の安心を同時に実現させましょう。