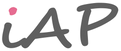経理・財務・税務のアウトソーシングを検討されている方に向けて、IPO準備の費用と経理支援サービスの特徴について解説します。
企業の成長段階のひとつであるIPO。
上場しようかと考えても、どのくらいの費用がかかるのか、税務や経理面での不安がある方も多いでしょう。
そこで今回の記事では、IPO準備にかかる費用と経理支援サービスについて解説します。
参考にしていただくことで、必要な予算の目安や今後の進め方を理解できるでしょう。

IPOの準備に必要な費用

それではさっそく、IPOの準備に必要な費用について見ていきましょう。
経理支援を利用せずにIPO準備を行った場合、主に次の5つの費用が必要となります。
①コンサルティング会社の報酬
まずはコンサルティング会社に支払う報酬です。
IPOでは上場手続きにおいて、コンサルティング会社を利用することが少なくありません。
審査に必要な書類の作成、決算開示体制の整備などの代行を依頼するためです。
コンサルティング会社に手続きを依頼する場合、年間500万〜1,500万円程度の費用がかかるのが一般的です。
上場手続きを委託するなら、コンサルティング会社への支払いを予算に含めなければなりません。
②監査法人の報酬
続いては監査法人への報酬です。
IPOの準備段階では、監査法人からの監査を受けなければなりません。
受ける監査は「ショートレビュー」と「準金商法監査」の2種類です。
【費用目安】
- ショートレビュー:150万円~400万円
- 準金商法監査:1,000万円~数千万円
かかる費用は企業の規模により変わりますが、種類ごとに上記の金額が目安となります。
③証券会社の報酬
IPO準備の段階では、費用として証券会社への報酬も考えておかなければなりません。
証券会社は上場手続きに関するアドバイスをしてくれる存在です。
報酬は年間で500万円から2,000万円ほどが目安となります。
上場した際の株式引受を行ってくれるのも証券会社であるため、IPOにあたって非常に重要な費用であると言えるでしょう。
④弁護士の報酬
弁護士にサポートを依頼する場合、弁護士への報酬も費用のひとつとなります。
IPOに関する法務は専門的であり、自社だけで行うことは難しいでしょう。
そこで多くの企業が、法律事務所に業務を依頼します。
発生する費用は500万円から2,000万円程度とされていますが、弁護士の稼働時間によって変動する仕組みであることが一般的。
弁護士への依頼は安価ではありませんが、正確かつスムーズにIPOを進めるためには利用を検討すべきです。
⑤申請書類の印刷費用
申請書類の印刷費用も、IPO準備段階における費用のひとつです。
上場に関する書類を印刷する場合は、ほとんどのケースで専門の印刷業者に依頼します。
その際の費用は200万円から500万円程度です。
申請書類は作成方法が決まっており、情報漏洩にも気を配らなければなりません。
そのため専門業者に依頼する方法が採用されます。
IPOの実施(上場)に必要な費用
IPOのために費用が必要となるのは、準備段階だけではありません。
実施にあたって次のような費用がかかります。
①新規上場の審査料
新規上場をするためには、審査料と呼ばれる費用が必要です。
審査料は上場する市場区分によって変わり、次のよう定められています。
上場審査料 プライム市場 400万円 上場申請日が属する月の翌月末日まで スタンダード市場 300万円 グロース市場 200万円 ※消費税額及び地方消費税額は含まれておりません。
ただし以前に上場申請や予備申請を受けたことがあり、3年以内に再度上場申請を行った場合は半額となります。
上場予定の市場区分ごとの料金を確認し、IPOの予算に組み込みましょう。
②新規上場の手数料
新規上場のためには手数料も必要となります。
手数料の金額は以下のとおりです。
料金 市場区分 プライム市場 1,500万円 上場申請日が属する月の翌月末日まで スタンダード市場 800万円 グロース市場 100万円
新規上場のための手数料も市場区分によって変わります。
審査料と同じく消費税や地方消費税は含まれない料金をご紹介しましたが、計算において100円未満は切り捨てとなります。
新規上場のためには上記の手数料も支払わなければならないと知っておきましょう。
③新規株式の公募・売出の費用
続いては新規株式の公募・売出のためにかかる費用です。
【公募・売出の費用[1]】
- 公募の場合 公募株式数×公募価格×0.0009
- 売出の場合 売出株式数×売出価格×0.0001
公募・売出のための費用は、市場区分に関わらず一律です。
しかしグロース市場では公募・売出ともに料金の上限が1,900万円と決められています。
④証券会社の引受手数料
上場を行うなら証券会社に引受手数料も支払わなければなりません。
引受手数料は証券会社に株式を購入してもらうための手数料のことを指します。
公募総額によって変わり、総額の5~9%であることがほとんどです。
⑤登録免許税
登録免許税も必要となる費用のひとつです。
会社としての登記を行うためにかかる税金のことを指し、「資本金組入額の7/1,000」と定められています[2]。
資本金の組入金額により支払う金額が変動しますが、税金として支払いましょう。
IPOの実施後に必要な費用

最後に、IPOを実施した際に必要となる費用についてご紹介します。
IPOは準備段階から実施にいたるまでさまざまな費用がかかりますが、実施した後にも支払わなければならない費用が残っています。
①証券取引所の年間上場料
上場をすると、証券取引所に年間上場料を支払わなければなりません。
年間上場料とは、上場を維持するための費用であり、金額は市場や上場時の時価総額によって変わります。
| 上場時価総額 | プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 | 支払期日 |
| 50億円以下 | 96万円 | 72万円 | 48万円 | 3月末日及び9月末日まで (左記の金額にTDnet利用料を加算した金額の半額ずつ) |
| 50億円を超え250億円以下 | 168万円 | 144万円 | 120万円 | |
| 250億円を超え500億円以下 | 240万円 | 216万円 | 192万円 | |
| 500億円を超え2,500億円以下 | 312万円 | 288万円 | 264万円 | |
| 2,500億円を超え5,000億円以下 | 384万円 | 360万円 | 336万円 | |
| 5,000億円を超えるもの | 456万円 | 432万円 | 408万円 |
金額は上記のとおりに定められていますが、消費税や地方消費税は含まれていません。
上場した場合、1年に1回、年間上場料を支払わなければならないことを覚えておきましょう。
②新規株式の発行費用
新規株式の発行にも費用がかかります。
| 料金 | 金額 | 支払期日 |
| 上場株券等を発行又は処分する場合 | 1株当たりの発行価格×発行又は処分する株券等×万分の1 | その新株発行等を行った日の属する月の翌月末日まで |
| 新株予約権の目的となる株式が上場株式である新たな新株予約権を発行する場合 | (新株予約権の発行価格×新株予約権の総数+新株予約権の行使に係る払込金額×新株予約権の目的となる株式の数)×万分の1 | |
| 上場株券等の売出しをする場合 | 売出株式数×売出価格×万分の1 |
新規株式の発行については、上場証券を発行する場合、新株予約権を発行する場合、上場株券などの売出を行う場合と3パターンに分けられます。
いずれも支払期日が決められているので、期日内に支払えるようにしましょう。
③株式事務代行の委託費用
続いては株式事務代行の委託費用です。
株式事務代行の設置は、会社法によって義務付けられているため必ず設置しなければなりません[3]。
委託費用は状況によって変わりますが、400万円から2,000万円の範囲内であることが多いでしょう。
株式事務代行機関は、株主名簿の作成・管理や株式配当の権利処理を行う重要な機関です。
義務でもあるため設置できるよう予算を立てましょう。
④監査法人の報酬
監査法人への報酬も費用のひとつとなります。
上場した企業は公認会計士もしくは監査法人から、監査証明を受けなければならないと義務付けられています[4]。
必要となる費用は1年間で500万円から1,500万円ほどです。
利用する機関によって異なる可能性があります。
⑤弁護士の報酬
上場後も弁護士への報酬は必要です。
弁護士は開示書類を法的な観点から確認し、正当であるかどうかを判断する役割を担います。
またクレームを受けた際の対応について相談することもあるかもしれません。
そのため多くの上場企業が顧問弁護士と契約しています。
報酬は相談内容や相談の回数により変わりますが、1年間で300万円から500万円と考えてください。
顧問契約は必須ではありませんが、上場後のリスク管理を考慮すると弁護士との契約を検討するのがおすすめです。
IPO準備に役立つ経理支援サービスとは?
経理支援サービスはIPO準備を費用面からサポートするサービスのことです。
財務・経理業務に関する業務を請け負い、コンサルティングも行います。
サービスの内容や流れ、利用時のポイントを紹介します。IPO準備を始める際の参考にしてください。
関連記事:IPO準備における経理支援サービスの重要性と導入効果について
サービスの内容と流れ
経理支援サービスにはIPO準備に役立つ次のようなサービスが含まれます。
【サービス内容と流れ】
- 企業の課題を洗い出し改善策を提案する
- 企業の規模に応じて管理体制を構築する
- 会計監査を行う
- 内部統制報告制度を構築する
- 上場企業としての体制を整備・運用する
IPOに向けてはさまざまな専門業者の力を借りることになりますが、経理支援サービスはIPOの準備段階から実施に向けてトータルサポートを提供します。
企業とともにIPOを進めていく存在であると言えるでしょう。
サービスのメリット・デメリット
経理支援サービスには多くのメリットがありますが、デメリットもあることを知っておきましょう。
【メリット】
- IPOを実践するためのトータルサポートを得られる
- IPO準備のための費用が経理支援によって俯瞰しやすくなる
- 長期的な戦略を立てられる
- 企業の価値やリスクを把握しやすくなる
- 専門家からの的確なアドバイスが受けられる
- 法務・税務上の問題解決に役立つ
【デメリット】
- 費用がかかる
- 相性によっては効果的なサポートを受けられない
IPO実践のためのトータルサポートを受けられること、調査や分析によって長期的な戦略を立てやすくなることがメリットです。
法務・税務上の問題を解決できることもあるでしょう。
しかしやはり、IPO準備で経理支援サービスを利用するには費用がかかります。
企業との相性が良くないと、効果的なサポートが受けられないことも考えられるでしょう。
利用するときのポイント
経理支援サービスを利用する際には、次の3つのポイントから業者を選んでください。
【ポイント】
- IPO実績が豊富であること
- 専門性が高いこと
- 費用が明確であること
IPO準備のために経理支援サービスを利用するなら、費用面も重要ですが、何よりもIPO実績が豊富であることが欠かせません。
さらに専門性が高い企業であれば、自社の課題解決のためにも役立ってくれるでしょう。
もちろん費用が明確であることも大切な要素です。
以上3つのポイントを意識すれば、IPO実施のために大きく貢献してくれることでしょう。
IPO準備では費用が必要でも経理支援サービスを利用して
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、IPO準備に必要な費用と経理支援サービスについてご理解いただけたと思います。
経理支援サービスの利用には費用がかかりますが、IPO準備を財務・経理面から力強くバックアップするサービスです。
私たちiAPでは、IPO準備のサポートから税理士サービス、内部統制の専門家による支援までを提供しています。
IPOを検討中の方は、業務サポートの一環としてぜひiAPのサービスをご利用ください。
[1]参照:日本取引所グループ:新規上場に係る料金
[2]参照:国税庁:No.7191 登録免許税の税額表
[3]参照:e-GOV:会社法(平成十七年法律第八十六号)
[4]参照:e-GOV:金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)